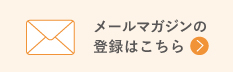悪いことばかりではない!?紫外線との正しい付き合い方
SUMMARY
- ・改めておさらい!紫外線が肌に及ぼす影響とは?
- ・紫外線を浴びることによって作られるのがビタミンD
- ・紫外線との上手な付き合い方を知ろう
- ・まとめ
3月に入ると徐々に増してくるのが紫外線の量。4月に急激に増え、5月には真夏並みになると言われています。「紫外線=美の大敵」というイメージが強いですが、近年では紫外線を浴びることの重要性が指摘されることも。
改めて紫外線が私たちに与える影響と対策について、医師の橋本知子先生にお話を伺いました。今一度、紫外線との付き合い方を見直してみましょう。
改めておさらい!紫外線が肌に及ぼす影響とは?
「地上に届く紫外線には、A波(UV-A)とB波(UV-B)の2種類があり、それぞれ肌に与える影響は異なります」と橋本先生。
「真皮まで達してじわじわとダメージを与え、肌の弾力やハリを失わせてシワやたるみの原因となるのがUV-A。いわゆる『光老化』です」
UV-Aは地表に届く紫外線の約9割を占めます。波長が長く、雲やガラスを通過してしまうため、曇りの日や家の中でも影響を受けてしまうそう。
「一方、肌を赤くさせるのがUV-B。レジャー紫外線とも呼ばれ、急激に浴びることで肌に炎症を起こし、やけどのように赤くなったり(サンバーン)、日焼けして黒くなったり(サンタン)するだけでなく、シミやそばかすの原因にもなります」
さらに老化を促進させるのが乾燥です。
「繰り返し紫外線を浴びることによって、肌は自分を守ろうとして角質をため込み、ゴワゴワと乾燥してしまいます。それによりスキンケアの効果も半減し、さらに乾燥が進んでバリア機能が低下。するとさらに乾燥が進むといった悪循環に…」
こういったトラブルから肌を守るには、日焼け止めがマストです。UV-Aの防止効果の度合いは「PA」で「+」が多いほど防止効果が高くなります。一方UV-Bを防ぐ効果を示すのが「SPF」で数値の値が高いほど防止効果が高くなります。
「地球温暖化に伴い、近年はどんどん紫外線量が増してきていると言われています。夏だけでなく、春先から、いえ、できれば一年中、家の中にいても日焼け止めをつけることが大切です」
紫外線を浴びることによって作られるのがビタミンD
一方で「紫外線を浴びることは健康的な体づくりに必要」と橋本先生。
「紫外線を浴びることで作られるのがビタミンD。食事でも摂ることはできますが、6~7割は皮膚で作られていると言われていて、地域や季節にもよりますが1日に30分ほど日光浴することが必要とされています」
ビタミンDは体のさまざまなところで働く栄養素です。
「カルシウムの働きを助ける成分で、健康の維持にとても重要です。ですが、現代人の多くがビタミンD不足という傾向にあります」
その理由は、美容のために紫外線を避けている人が多いこともありますが、生活スタイルの影響もあるそう。以下の項目に当てはまるものが多い人は、ビタミンD不足の可能性があると橋本先生は指摘しています。
外出する機会が少なく、家に閉じこもりがち
屋内で仕事や生活する時間が長い
運動はスポーツジムなど屋内でしている
インターネットで買い物をする機会が増えた
夜勤など、夜型中心の生活
勤務場所が駅に直結している
夏に外出するときは、日傘、帽子、サングラス、マスク、長袖、手袋などで全身を覆っている
日常的に日光にあたる時間が少ない人は、要注意です。
紫外線との上手な付き合い方を知ろう
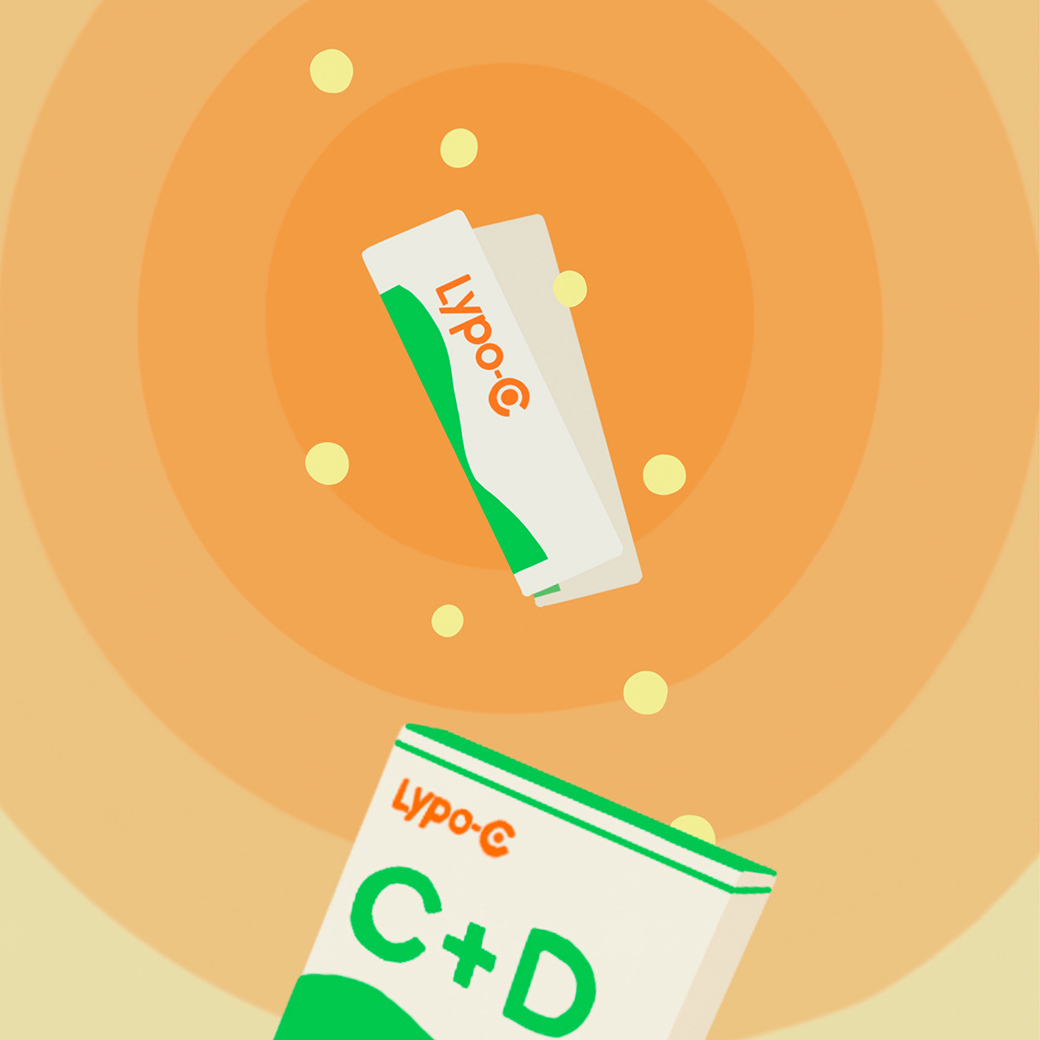
肌のためには紫外線を浴びないほうが良い、でも健康維持のためには紫外線を浴びなくてはならない。
では一体どのように紫外線と付き合っていくのが良いのでしょうか?
「最近ではビタミンDの生成を阻害しない日焼け止めも発売され始めています。そういった製品を取り入れてみるのも手でしょう。手に入らない場合でも、顔の肌の紫外線ダメージだけはどうしても避けたいので、顔だけはしっかり日焼け止めを塗るようにしましょう。そして紫外線を浴びたあとは、抗酸化作用が期待できるビタミンAやCをしっかり摂ることをお忘れなく」
また、ビタミンDの生成に関わっている紫外線はUV-Bだそう。つまりSPF値は低く、PA値が高い日焼け止めを選ぶのも目安の一つに。
「肌ダメージがどうしても気になる、夜勤でなかなか昼間に出かけられない…という人もなかにはいるはず。そんな人は、サプリメントでビタミンDを補いましょう。1日2,000~3,000IUほど摂取するのをおすすめします」
「Lypo-C Vitamin C+D」なら1包でビタミンCを1,000mg、ビタミンDを2,000IU摂取できます。ぜひ毎日の健康にお役立てください。
まとめ
紫外線の悪いところ、良いところを知ったうえで、上手に付き合っていくことが美容と健康には大切です。ただ、橋本先生のお話にあるように、多くの人がビタミンD不足の傾向があります。
日に当たる機会が少ない、体調に不安があるという人は、クリニックなどで血中のビタミンD濃度を一度調べてみるのがおすすめとのこと。今の自分の体の状態を把握したうえで、これからのケアを考えてみませんか?
橋本知子先生
臨床分子栄養医学認定指導医。高濃度ビタミンC点滴療法認定医。自身の乳がんをきっかけに分子栄養学に出合う。クリニックでは分子栄養学的な検査やカウンセリングを行い、病院に行くほどではないけれど不調をかかえている患者の治療にあたっている。